日銀下関支店長 岩下直行
支店長室の置物のひとつに、大内人形がある。直径15センチほどの球形の木地に漆を塗って作られた夫婦びなで、コロコロとしてかわいらしいデザインは最近流行のゆるキャラを連想してしまうが、れっきとした経済産業省指定の伝統的工芸品だ。いつも地味なガラスケースにしまわれていてあまり目立たないので、ひな祭りのこの季節だけは、ケースから取り出して部屋の正面に飾ることにしている。

大内人形の由来については、「大内弘世(ひろよ)が、京都からこし入れした奥方を慰めるために飾った人形」と説明することが多く、その話の出典として「陰徳太平記」という書物が挙げられている。実際には大内人形は、明治時代に復興された大内塗の技法を活かして大正時代に創作されたものなのだが、その際、弘世と奥方にちなむ伝承も参考とされたらしい。それにしても、人形を飾った程度で奥方の気持ちを慰められるものだろうか。疑問に思い、図書館でこの書物を借りて読んでみた。 「陰徳太平記」は16世紀、戦国時代の中国地方を舞台とする戦記物語で、17世紀に岩国藩の香川正矩(まさのり)・尭真(ぎょうしん)によって編さんされた。これに対し、大内弘世が活躍したのは14世紀、南北朝時代である。時代は大きく隔たっているが、この書物の中に、現在の山口市が開かれた経緯に関する伝承が、「山口興廃之事」として挿入されている。そこに、弘世と奥方をめぐる次のような逸話が書かれている。
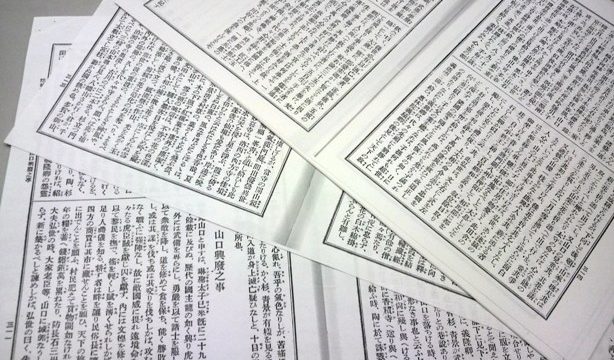
弘世の奥方は京都の貴族の生まれで、都のことが忘れ難く、いつも都の話をしては涙を浮かべていた。奥方を寵愛していた弘世は、「それならば都をこの地に遷してしまえばよい」として、京都に倣った都市計画を整備し、寺社を勧請し、道路に小石を敷きつめるなど、山口を西の京とすべく開発を進めた。芸術家や工芸品の職人などを都から招いたほか、住民の言葉や振る舞いも都風に改めさせようとして、各々の町ごとに6人ずつ、都から呼び寄せた子供を配置したという。
弘世は上京していた折に、いかにも都らしい情景を目撃していた。きこりが山からまきを運び出す際、ツツジやヤマブキの花を枝ごと折ってまきに添えて持ち帰り、それを子供たちが「一枝ちょうだい」と言って次々にもらい受けて遊んでいたのだ。この光景を見て弘世は、六歌仙のひとり、大友黒主の和歌「道のべの 便りの桜 折りそえて 薪や重し 春の山人」を思い出し、「姿や言葉のみならず、心も花の都人だなあ」といたく感動した。そして、山口に戻ってから、山口のきこりと子供にも同じように行動するようお触れを出したという。
もちろんこれらは伝承であるが、その後大いに発展する大内文化の起源に、「奥方を慰めたい」という弘世の心があったとすれば面白いことだと思う。そして、弘世をはじめとする当時の人々が、寺社建築などのハード面のみならず、ソフト面の充実にこそ大きな価値を見出していたという話は、現代を生きる我々にも参考になることではないだろうか。
(2011.3.2日 山口新聞掲載)
―PDF版は、こちらをご覧下さい。
